ここが大事!

● 商標権は「ブランド名」や「商品名」を守る権利
● 商標権の設定には「商標」と「ジャンル」の指定が必要
● 権利化には特許庁への出願が必要
● 有効期限は10年で、延長も可能
● 日本の商標権は日本国内のみで有効
● 「®」と「™」は商標を知らせるマーク
どういうこと?
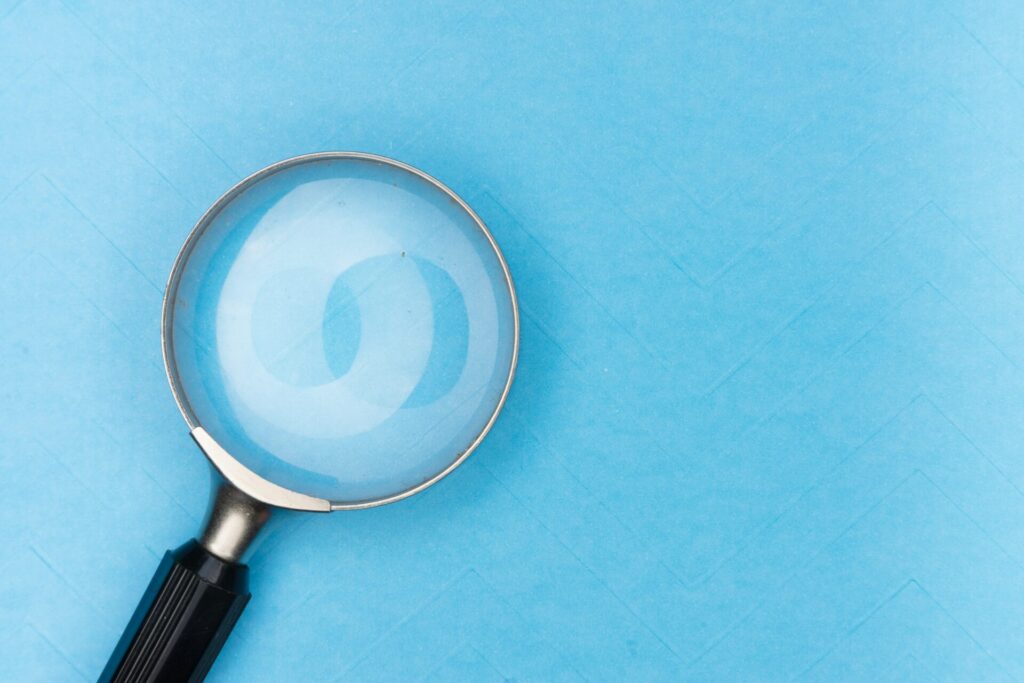
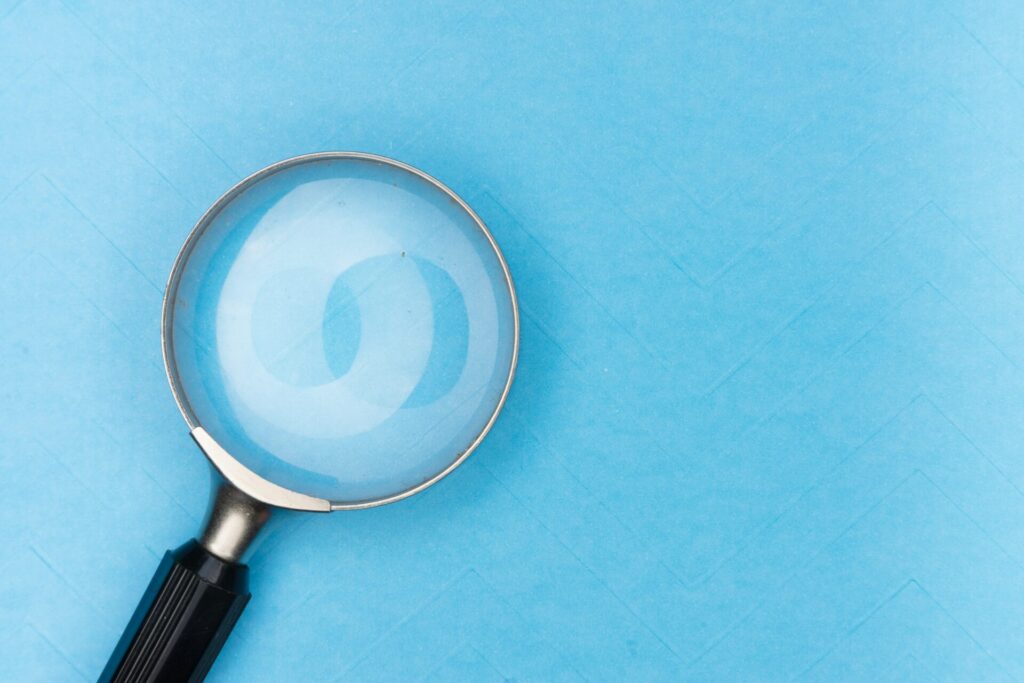

それではさっそく、それぞれのポイントについて詳しく見てみましょう。
商標権は「ブランド名」や「商品名」を守る権利
商標権とは、ブランド名や商品名、ロゴ、立体看板など、企業や個人事業主の商品やサービスであることを示す「標識」を独占的に使用できる権利です。
「商標」は英語で「trade mark (トレードマーク)」と言います。つまり、会社のトレードマークになるようなものが、商標権で保護される対象ということです。
たとえば、齧りかけのリンゴのマークといえばApple社、「スーパーマリオ」といえば任天堂社のゲームシリーズ、というように「アレといえばこの会社(商品)」と連想できることが商標の大きな役割であり、商標権を取得するうえでも大事なポイントになります。
商標権の設定には「商標」と「ジャンル」の指定が必要
商標権の有効範囲は「商標」と「ジャンル」によって決まります。
商標は上で説明したとおり、保護したいブランド名や商品名、ロゴなどのことです。
ジャンルとは、「スマートフォン」や「玩具」など、商標をどのような商品として使うかで、「指定商品又は指定役務」という項目で指定します。
登録された商標は、その商標と同じか類似している、かつ、指定されたジャンルと同じか類似している商標を他人が無断で使用することを防ぐことができます。
権利化には特許庁への出願が必要
商標権を取得するには、特許庁に商標出願をし、審査を通過する必要があります。特許とは違い審査のための請求(審査請求)をする必要はなく、自動的に審査が始まります。
出願から権利取得までの流れは次のとおりです。
商標登録したいものを、フォーマットが決められている「商標登録出願の願書」を作成します。
願書を特許著に提出(=出願)します。
出願後、順番に独鈷y超の審査が行われます。審査の内容は、書類に記載された内容に不備がないか(方式審査)、すでに同様のジャンルで同様の商標が登録されていないか等(実体審査)、についてチェックされます。
登録できない理由があるときは、特許庁から登録できない理由が書かれた「拒絶理由通知」と呼ばれる書類が送られてきます。書かれている内容を見て不備を補正したり、反論があれば意見書として主張できます。ただし、出願した商標そのものは補正できない等、補正できる内容には制限があります。
審査をクリアすると登録が認められます。ここまで来ればあと少し!
登録査定を受けてから30日以内に登録料を支払うことで初めて商標権が発生します。登録料を支払い忘れると、せっかくの出願が却下されてしまうので注意しましょう。
なお、商標権の更新登録料は10年分一括納付が原則ですが、5年分ずつ2回に分けた分割納付も可能です。
ついに商標権ゲットです!商標権は特許権や意匠権と違い、10年ごとに更新料を支払うことでずっと権利を維持し続けることができます。
日本の商標権は日本国内のみで有効
商標権は取得した国でしか権利は有効ではありません。つまり、日本で商標権を取得しても日本国内でしか通用しません。
海外でも権利を守りたい場合は、保護が必要な国ごとに意匠出願する必要があります。例えば、日本、アメリカ、中国で保護したいなら、それぞれの国で手続きをしなければなりません。
ただし、「マドリッドプロトコル(通称マドプロ)」と呼ばれる国際的な仕組みを利用すれば、一度の国際出願で複数の国に同時に出願したのと同じ効果を得られるため、手続きをある程度簡略化できます。
グローバルなビジネスを展開する場合は、戦略的にどの国で特許を取得するか考える必要があります。
「®」と「™」は商標を知らせるマーク
商品のパッケージやお店のロゴを見ると、「®」や「™」のような記号を見たことがありませんか?
これはどちらも一般的に「商標マーク」と呼ばれており、TM=Trade Mark(トレードマーク)の頭文字です。® はさらにRegistered Trade Mark の頭文字を取ったもので、つまり登録された(Registered)商標に付けられます。
しかし日本では商標マークについて法律上の決まりはなく、登録番号での表示が推奨されています。それでも慣習的には®マーク=登録商標とされているので登録されていない商標にむやみにつけるのは避けるべきでしょう。
よくあるギモン



まとめ



商標権は、ブランドや商品名を保護するための重要な知的財産権です。
ビジネスを始める際には、早い段階で商標について検討し、大切なブランド資産を守るための第一歩を踏み出しましょう。特に、インターネットの普及により、ブランドの価値がますます高まっている現代では、商標権の重要性は増すばかりです。







